目が覚めたら彼女がいなかった。それも当然、すでに時刻は正午を過ぎていたのだから。
は日課の散歩に行っているのだろう。ついでに加えると、彼女が出かけているということは、外界は晴れか曇りということだ。雨が降っている時にはさすがにすぐに戻ってくる。……まあ、天気が良かろうが悪かろうが、私にはさして興味のあることではないが。それにしても今朝――もう昼過ぎだが――は、
管理人注:↑はタイトルです。

良い気分だ。
ここ数日詰まっていた曲があったのだが、昨夜、突如としてラストまでの道筋が見えたため、夜を徹して書き上げたのだ。
そしてインクが乾くのを待つ間もなく、エネルギーの切れた私はオルガン脇の寝椅子に横になった。
……のは覚えているが、はて、私は一体何時まで起きていたのだろうか。
こんな疑問を持ったのは、寝椅子の傍にある小テーブルにコーヒーが置いてあったからだ。
自分で淹れた覚えはない。ということは
が淹れてくれたのだろう。つまり、私は彼女が起きてくるような時間――大体午前七時ごろだ――には起きていたということになる。
だが、していないわけがないであろう朝の挨拶も、会話も、何一つ覚えていない。
そして彼女が出かけていったのにもまったく気付かずに眠りこけていたということになる。いや場合によっては、彼女は私にちゃんと断って出かけたと思っているかもしれないのだ。ただ、私が一切覚えていないだけで。
(ううむ……)
冷め切ったコーヒーを一口啜り、私はぼんやりと天井を見上げた。
と、背後に衝撃を受けてカップを取り落としそうになる。
「おやおや、どうしたんだね」
突進してきたアイシャが、構ってくれと頭を摺り寄せてくる。そこで私は額をくすぐってやったり、紐を小刻みに動かしてやったりとひとしきり遊んだ。ゴロゴロと喉を鳴らして目を細めるアイシャを眺めながら、ふともこれくらい私に甘えてくれればいいのに、などということを思ってしまった。国民性なのか、彼女はいつでもどこかで一線を引いているように、礼儀正しく私に接してくる……。それが悪いことだとは言わないが、恋人というものは始終愛しい男にくっついていたがるものだと思っていただけに、いささか物足りないというかなんというか……。
「にー」
私の動きが止まったので、不満そうにアイシャが鳴いた。
「おや、すまなかったね。ところでお嬢さん、遊ぶのも結構だが、私は食事にしたいので、少し中断しても構わないかな?」
そういうと、彼女はしょうがないわね、とでも言うように、ひょいと床に下りた。
いつも思うのだが、アイシャは絶対に私の言っていることを理解していると思う。
キッチンに行くと、ナプキンをかけた皿があった。中には炒めたマッシュルームを添えたスクランブルエッグが用意されていたのだが、こちらもコーヒー同様すっかり冷めていた。
せっかくなので温かいうちに食べたかったが、致し方あるまい。昨晩の残りのスープを温めながらバゲットを切り、コーヒーを淹れなおして一人朝食――というか昼食というか――を食べた。
一人で食事をするのは慣れっこになっているはずなのだが、がいるのが当たり前になってしまった今では、こういう時、少しだけ寂しい。
しかし、我侭は言うまい。私が好き勝手に時間を過ごすのが『普通』だというのならば、彼女が規則正しく過ごすのもまた『普通』なのだ。なればこそ、互いの顔が合う時間がずれることがあるのはむしろ当然ではないか。私の起きている時間はずっと私の側にいるよう彼女に強要するなど実際無理だし、馬鹿げている。一人で出歩いていることについては心配しないわけではないが、人通りの多いところを選んで散歩しているようなので、強く止めるようなことは今後もしないつもりだ。とにかく、どこへ出かけようが、最終的に帰ってくるのは私のところなのだから。
スクランブルエッグを掬って口に放り込む。冷えたせいでバターがよりしつこく感じられた。そういえば以前にが、「電子レンジがないと作り置きができるのが限られちゃうのよね」とこぼしていた。
なんでもその電子レンジなる代物は、食材の中に含まれている水分を加熱することで食材のみを温めることができるのだという。中身が熱くなればそれを入れている器も同時に温まってしまうが、オーブンのように持てなくなるほど熱くなるわけではないそうだ。
食事というものは身体が要求するので仕方なく取っているので、自分ひとりであればパンと水でも構わないという私にとっては想像の埒外にある道具であるが、が欲しているとなれば、なんとかして作ってやりたいと思う。それに未来の技術を探るというのも面白そうではないか。
彼女が帰ってきたらもっと詳しい話を聞かせてもらおうと決めて食事を終えると、居間のソファに座った。読みかけの音楽雑誌を手に取るやいなや、アイシャが再び突進してきたので――ちゃんと私の食事が終わるまで大人しく待っていたのだ。やはりアイシャは賢い猫であると言えるだろう――片手で相手をしつつ、ページを繰った。
五時を過ぎたころ、玄関の方から音がしたので、が帰ってきたことに気付く。
我ながらあきれたことだが、それと察した私は考えるよりも先に足が玄関に向かっていた。扉を開けたら私がいたことに驚いたのか、彼女はちょっと目を見張ったがすぐににこっと笑って「ただいま」と言った。
「おかえり、おや、買い物をしてきたのか?」
彼女の手にリボンをかけた箱があることに気付く。それも、彼女のお気に入りである菓子店のものだ。
「そうなの。チョコレートって、定期的に食べたくなるのよね。あ、でも今日はただのチョコレートじゃなくて、ケーキなんだ。オペラなんだけど、エリックも食べてくれるでしょう?」
「そうだね、いただくよ」
甘いものは苦手ではない。ただ、わざわざ菓子屋に行ってまで買いたいと思うほど興味があるわけでもないので、普段は食べないだけなのだ。
ケーキの箱を受け取ってキッチンに置く。お茶の時間にするには時間が遅いので、これは夕食後のデセールにすることにした。
居間に戻ると、が自分の部屋に向かいながら帽子と外套を脱いでいるところだった。少々行儀が悪いが、新鮮な外の空気に触れて薔薇色に上気している彼女の肌はとても美しい。ふいに、身体の奥からむずむずするものが沸き起こった。
「?」
呼び止めると、なあに、と言いながら彼女が振り返る。
真顔のままに近付き、腕を広げる。
「や、ちょっと……!」
驚いた彼女が身を捩る間も与えずに、私は腕の中に愛しい女を閉じ込めた。
「なに、なに、どうしたの〜〜!?」
暖かい体温、柔らかな肉の感触。身をかがめて彼女の肩に額を預ければ、服の襞の間から、彼女が持ち帰った外の空気の匂いがした。
「ちょっと、エリック!?」
困惑が声に現れているが、は押し返したりはしない。本当になんて、可愛い子だろう。
私は彼女が優しくしてくれるのを期待して、哀れっぽい口調で言った。
「寂しかったんだよ。目が覚めたらお前がいなかったのでね」
「もう、甘えたなんだからー」
呆れたように言いながらも顔は笑っている。そして私の背中に腕を回した。
(ああ、幸せだ……)
充実した一日。
こんな日がずっと続きますように……。
そう誰にともなく、私は祈っていた。
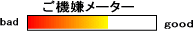
良くも悪くもない気分だ。
まあ、いつもの通りということだな。
今日は出かける予定はないので着替えを済ませると、簡単に食事を取ることにした。
卵を焼いているとアイシャが寄ってきたので、彼女の昼食も用意する。
出来上がったものをテーブルに運びながら、これでもいればもっと良かったのだが、などと思った。私のほうは不規則に生活しているので、起きたら彼女がいないということは、割合よくあるのだ。
食後は適当に時間を潰す。
作曲は一段落ついているし、今は特にやりたい実験はない。久しぶりにオルガンの手入れでもするかと腰を上げた。
自室はほぼ放ったらかし、居間とキッチンはよく使うところだけを片付ける、と言った私でも、楽器だけは粗雑に扱ったことはなかった。まあ、居間とキッチンはが来て以来は前よりは片付けるようにはなったが。彼女も手伝ってくれるしな。
作業を始める前に、散らかった楽譜をまとめて別のところに置き、インクやペンも元の位置に戻した。私が何かをし始めたので、自分も混ぜてくれとアイシャが近寄ってきたが、生憎猫の手を借りるわけにはいかない作業なので、書き損じた楽譜をぐしゃぐしゃに丸めて、オルガンがあるところとは逆の方向に投げた。
アイシャは一目散に追いかけて、前足で転がし始める。しばらくそうして遊んでいてくれ。
さて、掃除だ。
まずは表面の埃を払って濡れても大丈夫なところは水拭き、そうでないところは空拭きをする。
中を空けて、部品が弱っていないかをチェックし、その後は調律。時間はかかるが、美しい音色を保つには定期的にやらなければならない。今回は特別直さなければならない箇所はなかった。しかしどうして猫の毛というのは、こんな奥まで入り込むのだろうか。
掃除道具を片付けていると、玄関が開く音がした。
「ただいまー。エリック、起きてるー?」
が帰ってきた。
「いつまでも寝ていやしないよ。お帰り、」
物置から顔を出すと、彼女はにこっと笑った。今日の散歩も楽しかったらしい。
家に一人でいると寂しさを感じることもあり、そんな時にはを一人で外歩きさせるのは止めさせようか、などと思うのだが、こんな顔を見せられてはそうもできない。彼女が上機嫌でいるからこそ、私も幸せを感じることができる……。起こるかどうかもわからない危険を案じ、自らの利するところを優先させ、今現在ある幸福を捨てることなどしないよう、常に言い聞かせているのだ。
「掃除していたの?」
帽子を取りながらが問う。
「オルガンのだがね」
「じゃあ時間がかかったんじゃないの。お疲れ様。何か淹れましょうか?」
「だが、お前も疲れているんじゃないか」
「あら、わたしなんてちょっとその辺を歩いてきただけなのに」
とは笑った。
その日の夜は彼女を観客に、ピカピカに磨いたばかりのオルガンを披露した。
私が弾くだけではなく、尻込みする彼女の手を取って、一緒に簡単な曲を演奏してみた。
覚えが良い、とはお世辞にもいえないが、悪くもないので地道に教えようかと思っている。
……まあ、毎日続けられるかは、わからないが。
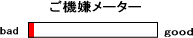
最悪な気分だ。
無力だった少年時代の夢を見たのだ。
家を取り巻いた村人たちがひどい言葉を浴びせながら、石を投げつけてくる。
私はただ家の中で震えて、嵐が過ぎるのを待っているだけだった。
夢の中の私は幼すぎて、大人たちが発する悪意に耐えられなかったのだ。
毛布をかぶり、身体を丸める。
しかしふと気がつくと毛布は消えていた。
壁や塀など、私を守ってくれる一切のものもなくなり、代わってうねうねと動く人の形をした黒い影に取り囲まれていた。
それらはただ私を追い詰めるためにそこにいる。
圧倒的な理不尽さに、私はその場を動くことができなかった。
感じるのは、ただ絶望だけ。
尽きることのない、絶望だけ……。
目を覚ました瞬間、自分がどこにいるのかわからなかったが、シーツの感触に気付いて夢を見ていたのだとわかった。
ひどく汗をかいていて気持ちが悪いほど。喉もからからだった。
夢だったのか、と安堵したのも束の間、腸が煮え返るほどの怒りがこみ上げてきた。
私はこれまで数え切れないほどの危険な目にあってきたが、何の仕返しもできず、されるがままでいたのは、幼少期のあの頃しかない。
自分が世の中からどれほど受け入れられないかを理解していなかったというのもあるが、決定的なのは子供ゆえに非力だったからだ。今ならばあのような扱いをされて黙っている私ではない。
ああ、思い出したくないのに、どんどん思い出してしまう。
今からボッシュヴィルへ赴き、私や母をさんざん追い詰め、あまつさえサシャをなぶり殺しにした村人たちに同じ苦しみを味わわせてやりたい!
上半身だけ起こしてくすぶる怒りを燃やし続けていたが、一日をこんな風に潰すのは意味がないと、私は寝台から抜け出した。頭を冷やそうと水風呂に入る。
だが、冷たい水でも、一度ついた炎はなかなか消えなかった。
幾人もの人間を殺した自分は、死んだら地獄へ行くだろう。
だが、彼らは?
優しいサシャを殺した奴らはどうなんだ?
サシャが犬だというだけで、無罪放免、天国へ行くというのか?
冗談ではない。
神が裁かないのだとしたら、私が裁いてやる。
そう決意するも、叶わぬ願いだと歯噛みする。
もう何十年も昔のことなので、ほとんどの奴らはすでに墓の下にいるはずなのだ。いかに私といえど、一度死んだ人間を二度殺すことはできない。
水風呂によって少しは落ち着いたものの、まだ胸の中で熾き火がくすぶっている感じがした。これは、やアイシャと戯れでもしない限り収まりそうにないと、部屋を出る。
そしてがいないことに気付いたのだが、アイシャもまたどこかに隠れてしまい、呼んでも出てこなかった。
なんてことだ!
ああ、どうして彼女たちはこんなにも勝手な行動を取るのだろうか!
私から多大なる世話を受けているのだから、その私のために大人しく家に篭っていようとは思わないのだろうか。なんて恩知らずな女たちなんだ。
憤慨しながら居間をうろつきまわる。
外に出たとは違い、私の『家』の中から出られないアイシャは、きっとどこか暗がりにでももぐりこんで寝ているのだろう。腹が空けば戻ってくるとは思うが、彼女は自分でネズミを取ることもできるので、いつ帰ってくるかはわからない。
そしては、だいたい決まった時間に帰ってくるが、なにしろ外というのは誘惑が多いものだ。いつもの時間に帰ってくるかどうか怪しいものだ。
それよりも、今までちゃんと帰ってきたことが不思議なくらいだ。
彼女はどうしてこんな場所へ戻ってくるのだろう。
こんな暗く陰気な……化け物の住処などに。
どうしようもない暴力の発作に囚われて、椅子を掴むと何度も壁に叩きつけた。
樫でできた頑丈なそれは、最初は歪むだけで中々壊れず、そのうち足が折れて砕けた。
破片が飛んで、顔に当たる。皮肉なことに仮面で覆われた側は仮面が弾いてくれたが、素顔のままの左の頬にはいくつかの傷ができた。
「……っは」
肩で息をしながら椅子の破片が散乱するなかに腰を下ろした。
空しい。
こんなことをしたって、が帰ってくるわけでもないのに。
だが、ああ、帰ってきたら、が帰ってきたら、二度と地上には出ないと誓わせよう。
だが、言葉だけの誓約など、信用できない。
新しい罠を仕掛けて、どうあっても出られないようにしてやる。
大丈夫だ、殺しはしない。
、私はお前を愛しているのだからね。
新しい罠は、当然に知られていないものにしなくてはならない。
罠や仕掛けの類は、思いついた端から書きとめていていて、それが相当数あるのだ。アイディア段階のものから、具体的な設計図までできたものまで、様々だ。
さあ、私の花を閉じ込めるにふさわしい檻はどれだ?
作業に熱中しているところにが帰ってくる。
部屋に入るなり彼女は目を丸くしてその場に立ち尽くした。
「ちょ……っ、どうしたの、これ!」
「」
「なんで椅子がバラバラになってるの。何をしたのよ、エリック!」
「」
「、じゃなくて! あああっ、血が出てるじゃない。本当に、何があったのよ」
彼女が小走りで来たので、私は待った。
は手袋を取って、私の頬に手を伸ばす。
私はその手首を握った。
「……エリック?」
怪訝そうに眉を顰める。心なしか、脅えの色がにじんでいる。
「、誓ってくれるかい」
「……何を?」
「二度と地上に出ないと。ずっと私の側にいると」
「……」
口を半開きにして、彼女は私を凝視した。
「誓うんだ」
私の催促に、彼女はわずかに身じろぎする。
は目を伏せ、そして小さく息を吐いた。
「エリック……」
次に目を上げた時、彼女は心配そうな、だけど凛とした表情をしていた。
軽く首を傾けて、一歩後ろに下がる。
逃げるのかと思って咄嗟に掴む手に力を込めた。
お前をどこにもやるものか!
「行くわよ」
どこへ、と問う間もなかった。
彼女は精一杯腕を伸ばして距離を稼ぐと、強く床をけって私にタックルをかけてきた。
「うお!?」
突然のことで受身を取る間もなかった。
私たちはもつれ合ったまま倒れこむ。絨毯を敷いている所だったのは幸いだった。そうでなければ堅い石の床で痛い思いをすることになっただろう。
「何をするんだ!」
私は叫んだ。
は私の上に乗ったまま、ひょうひょうと返す。
「タックル」
そんなことはわかっている。なぜ私にタックルをかけようと思ったのかを聞いているのだ!
「お前は……」
「不意をついて、別のことに意識を向けようかと思って。エリック、何だか荒れてるから」
「荒れてなど」
「あの椅子はなんなのよ」
彼女は視線で椅子の残骸を示す。
「で、どうしたの?」
は私の胸の腕に腕を乗せ、その上に頤を預けてた。行動は突拍子もないが、眼差しはいたって真剣だった。
「言わないと、ここから降りないからね。せいぜい私の体重プラス外出着フル装備……えーと、多分五キロくらい? で重い思いをしていなさい」
ふふふ、と芝居がかった調子の邪悪な笑みを浮かべた。
おかしな具合になった。いや、をどかすくらいなんて事はないのだが、なんというか……。
これで、ヒステリックに喚かれたり、平手打ちをされたとなると――殴る蹴るまでする女はあまりいないが、前二者をする女はかなりいるように思う――私も逆上したかもしれないが、こんな風にされてはどうしていいかわからなくなってしまう。
思い返せば、私が荒れていた――まあ、荒れていたとしか言えまいな、今までの行動は――原因は、そもそも夢見が悪かった、というだけのことで、それは、のせいじゃない。
「あぁ……」
もうどうにでもなれ、と力を抜いた。首だけ起こしていたのもやめると、暗い天井が目に入る。そこへ、いつ出てきたのか、アイシャが私の顔を覗きこんできた。逆さに見える猫も、いくぶん私を呆れ気味な表情で観ているように思えた。
なんだか自分の行動が滑稽に思えて、私は喉の奥で笑う。
「エリック?」
「ああ」
ふう、と息を吐き、目を閉じる。
「気は済んだ?」
「ああ」
「そう。じゃあ、椅子はわたしが片付けておくから、エリックはお茶を入れてくれる? その前に傷の手当をしましょうか。もう血は乾いているみたいだけど、念のため、ね?」
目を開けると、は優しい微笑を浮かべて私の返事を待っていた。
上手く操られている。
そんな風に思いもしたが、無闇に気分が悪くなっているよりはましと思い、頷いた。
ああ、本当に、彼女たちがいなくては、私は日々を過ごすこともできないのだ。
エリック氏の寝起き三態。
まあ、起きてからだいぶ時間が経ったりしてますが、外部刺激がないと起床時の機嫌をそのまま引きずりそうだなーと思って。
ちなみに、機嫌最悪の時に彼女が冷静だったのは、こういうことが初めてじゃなかったことと、放っておくと本当に閉じこめられ、最終的にはエリックとの関係が破綻するだろうとの読みがあって、頭フル回転させて、なんとか冗談で済ませようとしているのです。喧嘩の仲裁をしてくれる隣人がいないので、こういう時にはとても大変です。
戻る
![]()
![]()
![]()